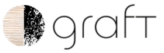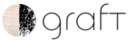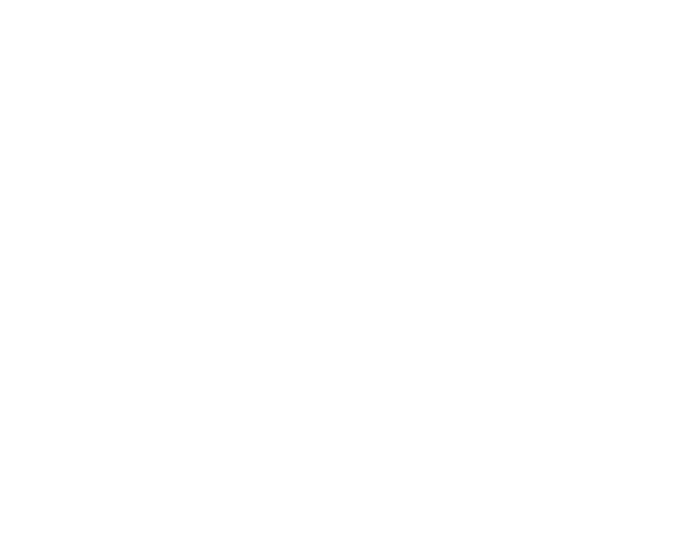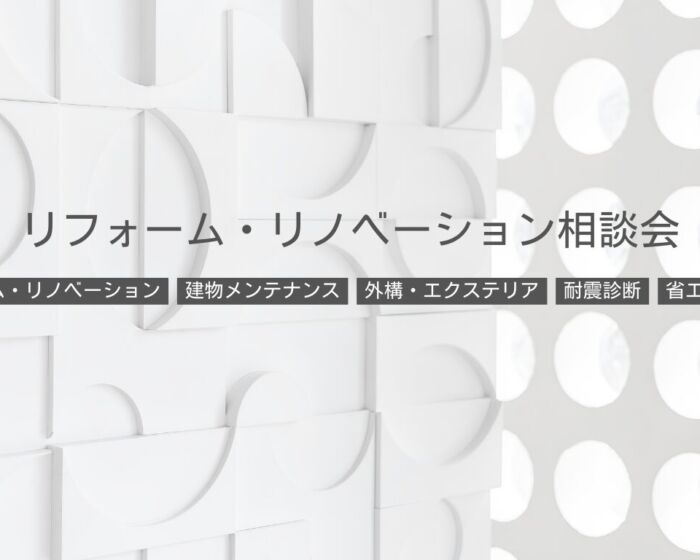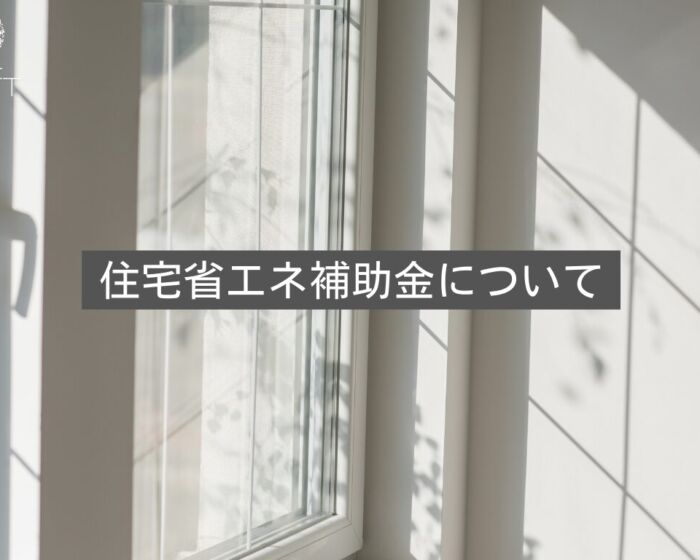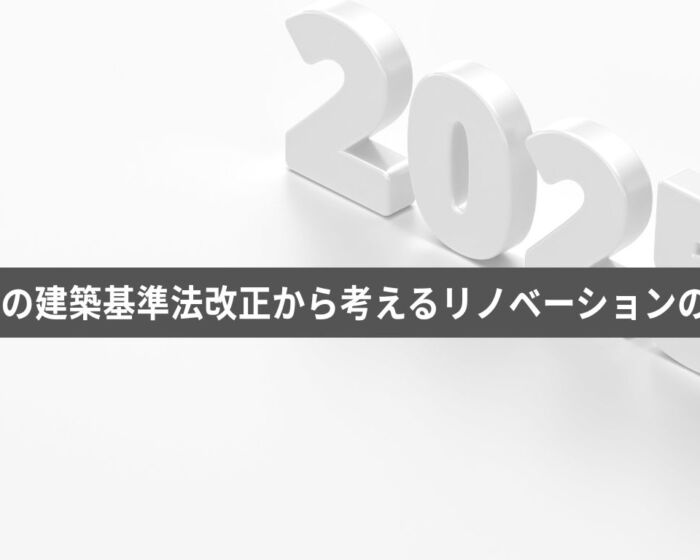空き家を相続したり、持ち家を長年使っていなかったりすると、こんな悩みが出てきませんか?
- 「この空き家、売るのが正解?それともリノベして活用するべき?」
- 「古い家だから、もう価値はないんじゃ…?」
- 「リノベーションして住めるのか、それとも費用がかかりすぎるのか知りたい」
結論から言うと、「売るか?リノベするか?」は、空き家の状態や立地によって判断すべき です。
この記事では、あなたの空き家が「売るべきか、リノベすべきか」を見極めるための判断基準 を解説します。
もくじ
Toggle1. まず考えるべきは「立地」|エリアによって選択肢が変わる
空き家の活用を考えるとき、最も重要なのが「立地」 です。
✅ 立地が良い(駅近・人気エリア)なら「リノベ向き」
✔ 交通の便が良いエリア(駅・バス停が近い)
✔ スーパーや学校など、生活インフラが整っている
✔ 最近、新築やリノベ物件が増えている
このような立地の空き家なら、リノベーションして自分で住むのはもちろん、賃貸や民泊などの収益物件として活用する選択肢もアリ!
→ GRAFTなら、耐震補強・断熱リフォームを加えて、快適に住める空間へとリノベーションできます。
⚠ 立地が悪い(郊外・過疎地域)なら「売却」も視野に
✔ 公共交通機関が少なく、車が必須なエリア
✔ スーパー・病院・学校が遠い
✔ 今後、過疎化が進む可能性が高い
このようなケースでは、リノベーションしても買い手・借り手が見つかりにくい可能性が高い ため、売却を検討するのが賢明 です。
2. 建物の状態|リノベできる家かどうかを見極める
「リノベできるかどうか」は、建物の構造や状態によって大きく変わります。
特にチェックすべきポイントは以下の3つです。
✅ 「リノベできる家」の特徴
✔ 1981年以降の「新耐震基準」を満たしている
✔ 基礎や柱がしっかりしており、大規模な補強が不要
✔ 間取り変更が容易な構造
このような家なら、リノベーションで快適に住めるようにすることが可能です。
GRAFTなら、事前に建築士が耐震診断を行い、リノベーション可能かどうかをチェックできます!
⚠ 「リノベ向きでない家」の特徴
✔ 基礎がひび割れ・腐食している
✔ 柱や梁が歪んでいる(傾きがある)
✔ シロアリ被害やカビがひどい
このような場合、リノベーションするよりも 解体して売却 or 更地にする方が現実的 なケースもあります。
3. 費用面の比較|リノベにいくらかかる?売った場合のメリットは?
「リノベする」といっても、気になるのは費用ですよね。
ここでは、リノベーションにかかるコストと、売却する場合のメリットを比較 してみます。
✅ リノベーションの費用目安
- 軽微なリフォーム(内装・水回り) → 300万〜600万円
- フルリノベーション(耐震補強・間取り変更) → 1,000万〜2,000万円
補助金や住宅ローンを活用すれば、自己負担を抑えながらリノベ可能!
→ GRAFTでは、補助金・助成金の活用アドバイスも行っています。
✅ 売却した場合のメリット
✔ リノベ費用が不要になり、手間もかからない
✔ 固定資産税・維持管理費の負担がなくなる
✔ 更地にすれば土地としての価値が上がることも
ただし!
築年数が古すぎると、「建物の価値がゼロ」 になり、土地価格だけでの売却になる可能性 も。
「売るか迷っている…」という場合は、まず査定をしてみるのも一つの方法です。
4. 「売る?リノベする?」判断基準まとめ
| チェック項目 | 売るべき? | リノベすべき? |
|---|---|---|
| 立地 | 過疎地域・交通の便が悪い | 駅近・人気エリア |
| 建物の状態 | 傾き・基礎の損傷あり | 耐震基準を満たしている |
| 費用面 | 修繕費が高額になる | 予算内でリノベ可能 |
| 活用方法 | 維持管理が難しい | 自宅・賃貸・民泊にできる |
この表を参考に、自分の空き家がどちらに当てはまるかチェックしてみましょう!
5. 「売るか、リノベするか」迷ったらGRAFTに相談!
「売るかリノベするか迷っている…」という方は、専門家のアドバイスを受けるのがベスト!
GRAFTなら、以下のサポートが可能です。
✅ 建築士による空き家診断 → リノベできる家かを見極め
✅ 耐震・断熱のアドバイス → 快適な住まいにできるかチェック
✅ 補助金・助成金の相談 → 費用を抑えてリノベ可能!
「この空き家、どうするべき?」と迷ったら、まずは無料相談を!
👉無料相談を申し込む
💡 まとめ
- 立地が良く、建物の状態が良ければ「リノベ向き」
- 立地が悪い・建物が傷んでいるなら「売却も視野に」
- 費用面や活用方法を考え、最適な選択を!
- GRAFTなら、プロの視点で「売る?リノベする?」をサポート!
空き家は放置すると**「固定資産税がかかる」「老朽化が進む」** など、デメリットが増えてしまいます。
早めに判断し、最適な活用方法を見つけましょう!